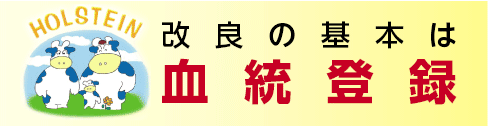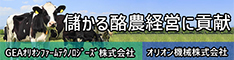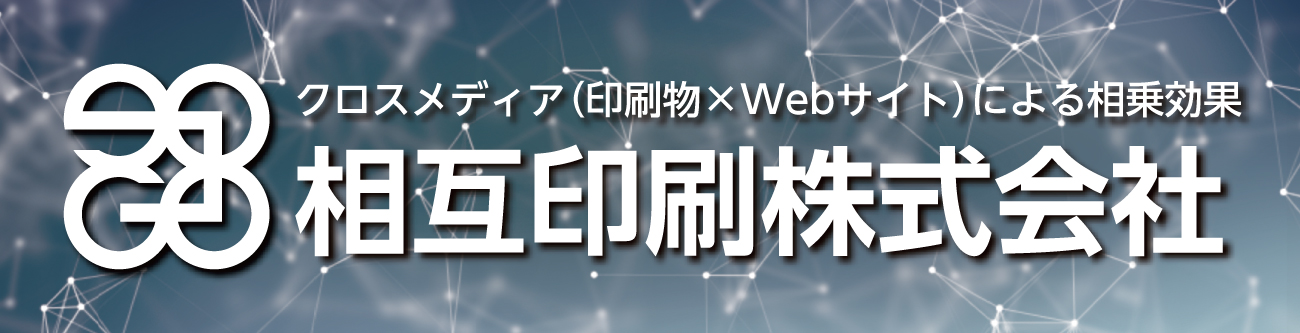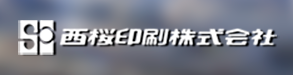全酪新報/2022年9月1日号
購読お申込みはこちらから
「高騰続く生産資材、配合飼料対策は予備費で検討」――自民党・早急な対応求める声相次ぐ
配合飼料価格等の高止まりが畜産・酪農経営へ甚大な影響を与えている現状を受け、森山裕自民党選挙対策委員長は、予備費での支援に向けて財務省と折衝中であることを明らかにした。8月24日に開いた総合農林政策調査会や農林部会等との合同会議の席上で説明した。政府が今後取りまとめる方針の物価高騰対策に向け自民党では、飼料高騰対策を盛り込むべく検討を進める。-詳細は全酪新報にてご覧ください-
お断り=本記事は9月1日号をベースにしておりますが、日々情勢が急変しており、本ホームページでは、通常の態勢を変えて本紙記事にその後の情報も加えた形で状況を掲載するなど、一部記事の重複などが生じることもあります。ご了承ください。
「消費拡大の取り組みが重要、生産者団体は生産抑制等も」――牛乳乳製品課・大熊課長
8月19日に行われた専門紙との懇談で、農水省牛乳乳製品課の大熊規義課長は、11月からの乳価引き上げ後の消費減退を想定した消費拡大の取り組みが重要だと強調した。Jミルクと共同で開始した「牛乳でスマイルプロジェクト」などを例に、農水省としても官民挙げて消費拡大へ取り組んでいく姿勢を示した。
その上で大熊課長は、需給安定には生産サイドの協力も不可欠と重要性を指摘。「今回の乳価交渉では、生産者団体も追加的な生産抑制や在庫対策に取り組む意志を示した上で交渉を行ったと聞いた。乳価引き上げが決まったことから、各生産者団体には早急に取り組みの具体化を進め、実行に移していただきたい。この成否は業界の命運を左右するものであり、乳業の協力も不可欠だ」との考えを示した。
一方、生産コスト上昇から、酪農経営が厳しい現状にあることへ理解を示した上で「酪農家は生乳生産だけでなく、地域社会にとっても重要な存在。酪農業を開始するには多額の資金が必要であり、現在営農している生産者に長く続けてもらうことが大事だ。特に家族経営では子どもたちに『継ぎたい』と思ってもらえる魅力的な環境にすることが重要。酪農家が安心して経営に取り組めるよう、現場の声をよく聴いて、どのような対応が必要か検討していきたい」と話した。
「2022年度第1四半期・生乳需給、牛乳1%減 緩和傾向で」――北海道の生産は2.3%増
農水省牛乳乳製品課が8月19日に取りまとめた2022年度第1四半期(4~6月)の生乳需給では、生乳生産は前年同期を上回った一方、5月の大型連休前半の大雨や気温低下から牛乳生産量は1%減。飲用需要の落ち込みを背景に生乳需給の緩和基調で推移した。秋からの乳価値上げ等も踏まえ、依然消費拡大の取り組みは重要性を増している。本紙など酪農専門紙と懇談する中で同課が説明した。
第1四半期の生乳生産量は197万8400㌧で前年同期比1.2%増。うち北海道は110万7100㌧(2.3%増)と上回る一方、都府県87万1300㌧(0.1%減)と前年度並み。用途別処理量は牛乳等向けが101万6100㌧(1.2%減)。乳製品向けは95万900㌧(4.1%増)で、液状乳製品向けは31万1800㌧(1.9%増)、チーズ向けは11万5800㌧(4%増)と好調に推移。脱粉・バター向けも50万8100㌧(5.5%増)と上回った。
消費面では、加工乳を除き、飲用牛乳等は減少。乳飲料、はっ酵乳についても下回った。乳製品生産量は、仕向け量の増加から脱粉4万3100㌧(7.1%増)、バター2万1千㌧(5.5%増)とどちらも増加した。期末在庫量は脱粉が10万4100㌧(15.2%増)と大幅に増加。一方、バターは4万1800㌧(1.1%減)だった。
大熊規義牛乳乳製品課長は第1四半期の生乳需給について、生乳生産が増加する一方、依然続く業務用需要の低迷や5月の大型連休中の大雨等により飲用需要は振るわず、需給緩和が継続していると説明。その上で夏場の需給動向について「今年は例年にない早さで梅雨が明けた。一部地域では猛暑により乳量の減少などの影響が見られるが、全体ではひっ迫と緩和基調が入れ替わる形となっている。引き続き情報収集し、今後の需給状況を注視していく」と述べた。
「2023年度予算概算要求、畜産・酪農経営安定対策は同額」――加工原料乳のナラシ事業は増額要求
農水省は8月31日、2023年度農林水産予算総額2兆6808億円(前年度予算比4031億円、17.7%増)とする概算要求を示した。酪農関連では、牛マルキンや加工原料乳生産者補給金等を支援する畜産・酪農経営安定対策に今年度同額の2234億円、加工原料乳生産者経営安定対策事業(ナラシ)は14億円増額の32億円を要求。このほか、ICTを活用した畜産経営体の生産性向上、国産飼料の生産拡大・飼料の安定供給を支援するメニューなど、現行対策も含めた予算確保・増額を目指す。
また、23年度概算要求では水際検疫の徹底や伝染病まん延防止に向け、家畜衛生等総合対策予算を引き続き要求。なお、総合的なTPP等関連政策大綱を踏まえた経費、食料安全保障に向けた対応に係る経費は事項要求として提出し、予算編成過程で検討する。
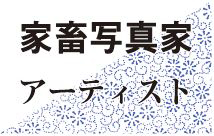 「牧場で輝く家畜の命」連載⑯瀧見明花里さんの写真エッセイ
「牧場で輝く家畜の命」連載⑯瀧見明花里さんの写真エッセイ

「キナコ」の娘「ダイズ」(村上牧場、北海道せたな町)

お隣さんとも仲良し(左がダイズ)
前月号にて登場した牛、キナコが出産してから1ヶ月。生まれてきた子牛の成長を見守りに牧場へ行ってきました。
子牛の名前は「ダイズ」。「かなり神経質だから、可愛がっていってね」という伝言を預かり、撮影の前に戯れるところからスタート。「覚えてる?」そんな呼びかけに答えるかのように顔を出してくれました。隣の子牛がベロリと舌を伸ばしてくるのに対し、控えめにお鼻をチョンとくっつけてくるダイズちゃん。私が触れようとすると、すぐに頭を引っ込めて奥へ行ってしまいました。
怪しい人間ではないアピールをして警戒を解くために、しばらくお隣の子牛と戯れていると、「大丈夫なのか?」と調査をしに再び寄ってきたダイズちゃん。多少の警戒心が残りながらも、2頭に混じって戯れ合うことができました。もっと側にいたいという気持ちとは裏腹に、あっという間に日が沈み、「また会いにくるから、忘れないでね」と告げて車を走らせたのでした。(全酪新報では毎月1日号に掲載しています)
プロフィール
瀧見明花里(AKAPPLE)

農業に触れるためニュージーランドへ1年3ヶ月渡航。2017年より独立。『「いただきます」を世界共通語へ』をコンセプトに、牛、豚、鶏をはじめとする家畜動物を撮影、発表。家畜の命について考えるきっかけを届けている。
※写真の無断使用はご遠慮下さい